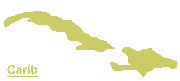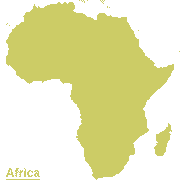私は昔、立花隆のファンだった
上杉隆について書いたのでついでに(?)立花隆について書いて
みよう。正直言うとある時期まで私は立花さんのファンだった。特に渡辺昇一氏との対談「論駁」での論理のゴリ押しで「勝つ」みたいな姿勢には大いに共感を
持った。何故なら当時の私も論理のゴリ押しで論争に勝つことに怪漢を、いや快感を覚えていたからだ。
残念ながら一度もお会いしたことがな
い。私が朝日新聞社員だった頃、立花氏が最も寄稿されていたのが朝日新聞であり、いつでも(コネを介して)会えると油断していた。また広告の仕事で講演会
の依頼をすれば簡単に呼べるだろうとも考えていた。結局、お会いする前に私が朝日を辞めたので会うことはできなかった。
私が非難している
のは国家破産論者としての立花隆氏である。この点に関しては日本最低レベルだと考える。さらに1995年に朝日の紙面で「日本の国家破産はさけられない」
と予言しながら未だに実現しないことを謝罪・訂正しない、それは正に立花氏が80年代初期、激しく攻撃した知的誠実さの欠如である。
立花
氏はバブル末期は冷静な発言をしていた。例えば「NTTの時価総額がATT、IBM、GMの時価総額合計より大きい。こんな馬鹿げた話があるか」と実に辛
辣な発言をしていた。では何故、「おかしく」なったのか?ある人は私生活の変化を挙げた。「立花さんは糟糠の妻を捨てて病院長の娘と再婚した。つまり、も
う文章で生計を立てる必要がなくなったのさ」と皮肉をこめていった。ちなみに彼は本当に糟糠の妻(長年、苦労を共にした妻という意味)という表現を用い
た。朝日の社内ではそうした表現が割と使われた。その程度には知的であった。
wikiの記述を読むと立花氏を朝日に取り込んだのは筑紫哲
也氏だと言う。この人が朝日ジャーナルを扇情的左翼過激雑誌に変貌させ、それを嫌った朝日経営陣により追放されてTBSに移ったと言われている。筑紫哲也
氏は退社の前に「TBSに移っても私は死ぬまで朝日人です」という長島のようなコメントを社内報で書いていた。その後釜に朝日経営陣により無理矢理すえら
れたのが下村満子氏である。社内ではマンコというニックネームで知られていた。いや、本当の話である。
実は私は筑紫哲也氏も下村満子氏も
お会いしたことがある。「英語を身につけて国際人」という広告企画をやったのだが、広告が十分に集まらず、社内の人間を講演者に使って安くあげる必要が
あったのだ。最初は筑紫哲也氏に交渉したのだが「ボクがそんな講演会に出たら外報部の連中が笑いますよ」と言い訳され、体よく逃げられた。編集の連中が広
告営業を見る冷たい視線には慣れていた私だが筑紫氏の返事ほど蔑視が透けて見えて不愉快になったことはない。筑紫氏は経営陣にも編集内部でも嫌われていた
が、「あの態度」では嫌われて当然だ。
次に講演を依頼したのが下村満子氏である。下村さんも乗り気ではなかったのだが最終的には引き受け
てくださった。下村さんと別の誰かの対談形式の講演会は無事に終えたのだが、意外な事に下村さんは本当に英語の達人だった。私に対し「竹本さんが自分で司
会して講演すれば安く上がるのに」という猛烈な皮肉を浴びせた。しかし下村さんの英語力は私よりずっと上だったので私はあえて反論をせず講演会進行表の説
明をしたのだった。
ところでwikiによると立花隆氏は以下のようなコメントをされたらしい。
引用(wiki)
1992
年、朝日ジャーナル休刊時に編集長を務めていた。評論家の立花隆氏は下村満子の編集長ぶりに対して批判的であり「記者としてはなかなかの人と思っていた
が、編集長としての資質をいささか欠いていたのではないか。」「どう考えても朝日ジャーナルをつぶしたのは、下村満子編集長である。」「彼女の編集長とし
ての能力の欠如があの雑誌をつぶしたのである。」と厳しく論じている。(出典:1995年文芸春秋発行・立花隆著「ぼくはこんな本を読んできた」ページ
214)
引用終わり
はあー、立花氏は下村さんがジャーナルの有終の美を飾るために選ばれたのをご存じないらしい。実際、下村さんは社内報で「経営幹部に押しきられてジャーナル編集長をやることになった」と最初からヤル気のなさを表明されていた。
そして下村氏も社内の軋轢に嫌気がさしたのか中途退社する。この人も大きな病院を経営するお父さんのもと良家の子女として育てられた。
立花氏もそうだし下村氏もそうだが、経済的に非常に安定した家庭に育つ、あるいは安定した環境になるとIQは高くても知的なハングリーさを失うのかなと私は思う。ソクラテスが痩せていたのは悪妻を別にしてもそれなりの理由があったのだ(笑)。